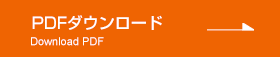導入から4年で、1万1千人が利用。KDDIの現場改革を支えたBPMS


KDDI株式会社 様
| ■業種 | 電気通信事業 |
|---|---|
| ■業種詳細 | 移動電気通信業、長距離電気通信業、インターネット利用サポート業 |
| ■従業員数 | 64,636名(連結ベース、2025年3月31日現在) |
コア技術統括本部 オペレーション本部 運用DX推進部 エキスパート
新藤 雄一郎(しんどう ゆういちろう)氏
コア技術統括本部 オペレーション本部 運用DX推進部 DX開発3G コアスタッフ
小峰 章仁(こみね あきひと)氏
コア技術統括本部 オペレーション本部 運用DX推進部 DX開発3G コアスタッフ
野村 竜也(のむら たつや)氏
課題・背景
■現地出動エンジニアの待機時間が多く作業効率が課題
■保守支援システムがなく、同じ通信局舎にも関わらず回線サービスごとに名称が異なっていた
導入の狙い
■現地対応保守業務の最適化
■保守運用システムの一本化
導入サービス
■BPM(intra-mart)

“IT化されていない作業を、intra-martで一網打尽にしたい。”
新藤 氏
全国30万基地局の保守業務最適化が急務になっていた
KDDIでは、安心・安全な通信サービスを提供するため、24時間365日体制で運用監視を行い、全国に展開するネットワークセンターの局舎設備や通信設備、基地局設備の保守・保全を実施しています。基地局や回線に生じたトラブルのうち、遠隔で復旧可能なケースは迅速に対応できますが、物理的な復旧作業が必要な場合はエンジニアが現地に向かう必要があります。これら現地対応保守業務を最適化するために導入したのが、現在アースリンクに開発依頼をしているintra-martを活用したシステムです。
―― 現地対応保守管理システムの構築を検討したきっかけを教えてください
システム導入前は、まとまった現地保守支援システムがなく、回線サービスごとに局舎名がバラバラでした。同じ局舎にも関わらず、異なる名称で運用されていたのです。そして、現地復旧や保守作業は、監視センターと現地エンジニアが電話で連絡を取りながら進めていました。
全国に広がる基地局の数は約30万拠点、保守に携わるエンジニアもかなりの人数です。エンジニアによって対応できる業務が異なるうえ、どのような作業を行うか監視センターから電話で指示する必要がありました。しかも、センターで同時に対応できる件数には限りがあり、エンジニアが現場に到着しても「電話がつながるのを待つ」待機時間が発生していたのです。現地対応保守業務では、無駄の多い運用が課題となっていました。

“約30万の基地局が、このシステムに支えられています。”
小峰 氏
―― アースリンクを選んだ決め手は?
実は、過去に社内で実施したBPM製品のコンペで、intra-martが他社に大きく後れを取ったことがあります。その結果を知った知人が「intra-martなら、もっとできるはずなのに!」と、非常に悔しそうにしていたのが印象的でした。そこで、今回のプロジェクトでコンペを行うことになったとき、彼から「intra-martの開発に強いSI」として紹介されたアースリンクにもご参加いただきました。
アースリンクを選んだ決め手は、その“バランスの良さ”にあります。intra-mart自体はユーザーフレンドリーでエンハンス耐性が高い優れた製品だと認識していましたが、他のベンダーは「求めていない提案が多くて、価格が高い」か「安価だがPJ必要ロールの人材不足」というパターンが多かったのです。アースリンクは必要最小限な提案をするうえ、若手技術者はもちろん、マネージャーもしっかりと製品を熟知していた点が魅力でした。
4年間で1万1千人が利用する大規模システムへと成長
―― システムの導入前後の変化をお聞かせください
現地対応業務における「アサイン」から「復旧指示」、「現地操作」、「完了報告」まで、すべてを一つのシステム上で完結できるようになりました。特に大きな変化は故障対応の方法です。従来は現地対応エンジニアが物理交換等をしたのち、監視センターへ電話で無線機の操作等を依頼していましたが、現在はエンジニアがスマホからシステムで確認、操作できます。出動前に作業内容を把握できるため現地対応がスムーズになり、よほど複雑な作業でない限り電話による問い合わせはありません。センターとエンジニアのやり取りが減少した結果、復旧にかかる時間は約半分に短縮されています。もちろん、作業効率向上だけでなく、センター側のコストも大幅に削減されました。開発開始から4年が経過し、現在は1万1千人がこのシステムを利用しています。ゼロベースでスタートしたにもかかわらず、短期間でこれほどの人数が利用するようになった社内のシステムは他に思いつきません。
―― 開発頻度はどの程度でしょうか?
大きなアップデートは四半期に1回ですが、要件が日々降りてくるので2週間に1回くらいの頻度で小さなリリースをしています。BPMのコンセプトは現在の業務をつなげていくことであり、PDCAのサイクルを回していかなければ意味がありません。そのため、常に検証しながら、改善点に応じたアップデートが求められます。しかも、半年後にはニーズが変わるケースもあるため、開発スピードも重要です。アースリンクは我々の求めるスピード感を理解し、しっかりと寄り添った対応をしてくれるので助かります。

“アースリンクは、このシステムにとってなくてはならない存在。”
野村 氏
分断されている運用業務を、intra-martでつないでいきたい
―― 今後の方向性をお聞かせください
めぼしいものはこのシステムと連携できるように消化してきたつもりですが、まだ単独でIT支援もなしに行われている業務が散見されます。また、似たような業務が既存の組織構造で別業務として扱われているなど無駄の多い状態です。そのため、構築したシステムを最大限に活用して運用プロセス全体を最適化し、最終的にはシステムの一本化を目指します。さらに、このシステムを社内の基盤として進化させられたら良いですね。昨今のKDDIでは“つなぐ”をキーワードに活動していますが、社内でバラバラになっている業務をつないだり、縦割りになっている事業をつないだりしていきたいです。
そして、究極をいうと、同業他社と保守運用を一緒にできれば理想的だと思います。全国各地にある基地局は増えていく一方ですが、エンジニアのリソースは有限です。勝負領域と、協調領域を切り分けることで、業界全体の効率化実現を目指していきたいと考えています。